甚目寺観音は、愛知県あま市にある真言宗智山派の寺院です。「尾張四観音」のひとつに数えられ、推古天皇の時代に創建された古刹と伝えられています。南大門や三重塔は国の重要文化財に指定されており、隣地には式内社の漆部(ぬりべ)神社が鎮座しています。
旅行先について
地図
旅行先の概要
| 御本尊 | 聖観世音菩薩 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県あま市甚目寺東門前24 |
| 交通 |
名古屋鉄道津島線「甚目寺駅」から徒歩5分、又はあま市巡回バス(東部巡回ルート)乗車3分、「甚目寺観音前」バス停下車 名古屋第二環状自動車道「甚目寺北IC」又は「甚目寺南IC」から車で5分 |
| 拝観料 | 無料 |
| 駐車場 | 境内南大門脇に舗装された無料駐車場あり【身障者用区画併設】 |
| URL | https://jimokuji.or.jp/ |
| 連絡先 | 甚目寺観音 052-442-3076 |
歴史・由来
甚目寺観音は、愛知県あま市にある真言宗智山派の寺院で、山号を「鳳凰山」といいます。
縁起によれば、推古天皇5年(597)、伊勢国の漁夫であった甚目龍麿(はだめたつまろ)が入江で漁をしていたところ、紫金の観音像が網にかかったため、堂を建ててこれを安置したのが始まりで、その後天智天皇の病気平癒に効験があったことから勅願寺になったということです。
天治元年(1124)には大地震の被害を受けますが、建久7年(1196)に聖観上人が勧進して伽藍の造営を始め、建仁元年(1201)に再興を果たし、この寺の中興開山となりました。今に残る南大門(仁王門)も、建久7年(1196)に源頼朝が梶原景時を奉行に命じて再建したものと伝えられ、鎌倉時代の見事なこけら葺きの楼門として国重要文化財に指定されています。
また、弘安6年(1283)に一遍上人がこの寺を訪れ、7か間にわたる行法を修したとき、毘沙門天の夢のお告げを受けた萱津宿の徳人(金持ち)たちが供養のために食べ物を施したことが、『一遍上人絵伝』の中に描かれています。
江戸時代には尾張藩主・徳川義直から寺領300石の寄進を受け、荒子観音、龍泉寺、笠寺観音とともに「尾張四観音」のひとつとして栄え、境内に寺坊36坊を数えました。境内の三重塔も江戸時代の寛永4年(1623)、名古屋の両替商・吉田半十郎政次が寄進したもので、高さは25メートルもあり、国重要文化財に指定されています。
隣地に鎮座する漆部(ぬりべ)神社は、もと甚目寺の鎮守社だったものが明治時代の神仏分離令により独立したものですが、全国でも珍しい漆を祀る延喜式内社です。
車椅子で旅行するポイント
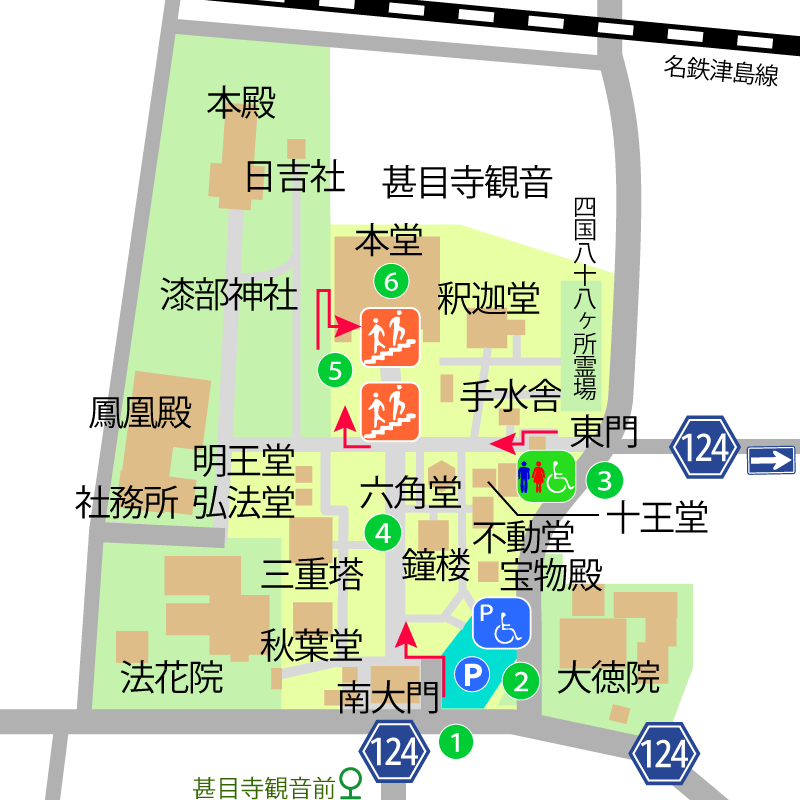
| 愛知県道124号西条清須線 甚目寺観音前バス停 法花院 大徳院 甚目寺観音南大門 秋葉堂 三重塔 弘法堂 明王堂 宝物殿 鐘楼 六角堂 不動堂 十王堂 東門 手水舎 釈迦堂 四国八十八ヶ所霊場 本堂 漆部神社社務所 鳳凰殿 本殿 日吉社 名鉄津島線 |
移動のしやすさ
★★★★★
バリアフリーの状況
甚目寺観音は平地にあり、境内の参道もほぼコンクリートで舗装されていて車椅子でも移動がしやすい。アスファルト舗装済みの駐車場には身障者用区画があり、境内東門脇にバリアフリートイレもある。また、参道や本堂の階段にも迂回可能なスロープが併設されている。
周辺の名所・観光スポット
清洲城
「清洲城」は、室町時代の応永12年(1405)、尾張守護の斯波義重によって築城されたとされる城郭です。織田信長はこの城を改修の上で自身の居城とし、今川義元を打ち破ることになる「桶狭間の戦い」に出陣しました。その後、慶長15年(1610)に名古屋城の築城が開始され、清須から名古屋へ城下町が移転する「清洲越し」が実現するまで、織田信雄や福島正則、徳川義直らが城主を務めています。平成元年(1989)、清須古城跡の五条川を挟んで反対側に、当時の姿をイメージした鉄筋コンクリート造の模擬天守「清洲城天守閣」が建造されました。
【敷地内に身障者用トイレ・スロープあり。ただし、館内入口は階段のため、隣接の「清洲城芸能文化館」から入るが、上層に登るにはやはり階段しかないため、以降の車椅子移動は不可。手帳提示で障害者本人無料・付添人1人半額の割引制度はある。】
■参考リンク:https://www.city.kiyosu.aichi.jp/shisetsu_annai/kanko_shisetsu_sonota/kiyosujo.html

 東京周辺 神社仏閣どうぶつ案内 神使・眷属・ゆかりのいきものを巡る
東京周辺 神社仏閣どうぶつ案内 神使・眷属・ゆかりのいきものを巡る





