久米寺は、奈良県橿原市にある真言宗の寺院で、薬師如来を本尊としています。『今昔物語集』にある久米仙人ゆかりの寺として知られます。境内の多宝塔は国の重要文化財です。この寺では毎年5月3日に「練供養」が行われ、「来迎橋」の上を二十五菩薩が渡ります。
旅行先について
地図
旅行先の概要
| 御本尊 | 薬師如来 |
|---|---|
| 所在地 | 奈良県橿原市久米町502 |
| 交通 |
近畿日本鉄道橿原線・南大阪線・吉野線「橿原神宮前駅」から徒歩5分 京奈和自動車道「橿原高田IC」から車で10分 |
| 拝観料 | 境内自由。ただし、本堂内陣拝観の場合は拝観料400円。 |
| 駐車場 | 境内山門脇に未舗装の普通車用無料駐車場、境内南西隣地にバス専用無料駐車場あり |
| URL | https://www.city.kashihara.nara.jp/soshiki/1021/1/2/3/3652.html |
| 連絡先 | 久米寺 0744-27-2470 |
歴史・由来
久米寺は、奈良県橿原市にある真言宗御室派の寺院で、薬師如来を本尊としています。
『和州久米寺流記』は、聖徳太子の弟が薬師如来に願掛けして眼病平癒したことから、来眼皇子(くめのみこ)と号するとともに、七堂伽藍を建てて「来眼寺」と称したと伝えています。
また、『今昔物語集』によれば、龍門寺に籠もって修行の末に仙人となって空を飛んだ久米が、洗濯をする女のふくらはぎに見惚れて墜落し、ただの凡夫となって女と暮らしていたところ、役人の言辞に一念発起して再び修行に成功し、仙術をもって平城宮の造営工事を助けました。その功績により朝廷から免田を賜ったことから、免田の利得によって建てたのが「久米寺」であるといいます。
さらに、弘法大師空海はこの寺で『大日経』を感得し、後に入唐して密教の奥義を究め、帰国して真言宗の開祖となったことから、「真言宗発祥の地」ともいわれます。
境内には江戸時代の万治(まんじ)2年(1659)に仁和寺から移築した「多宝塔」があり、桃山時代の様式を残す貴重な建造物として国の重要文化財に指定されています。
毎年5月3日には、境内の護国道場から本堂までの間に組まれた木の桟橋「来迎橋」の上を二十五菩薩の面をつけた人たちが渡る「練供養」とよばれる行事も催されます。
車椅子で旅行するポイント
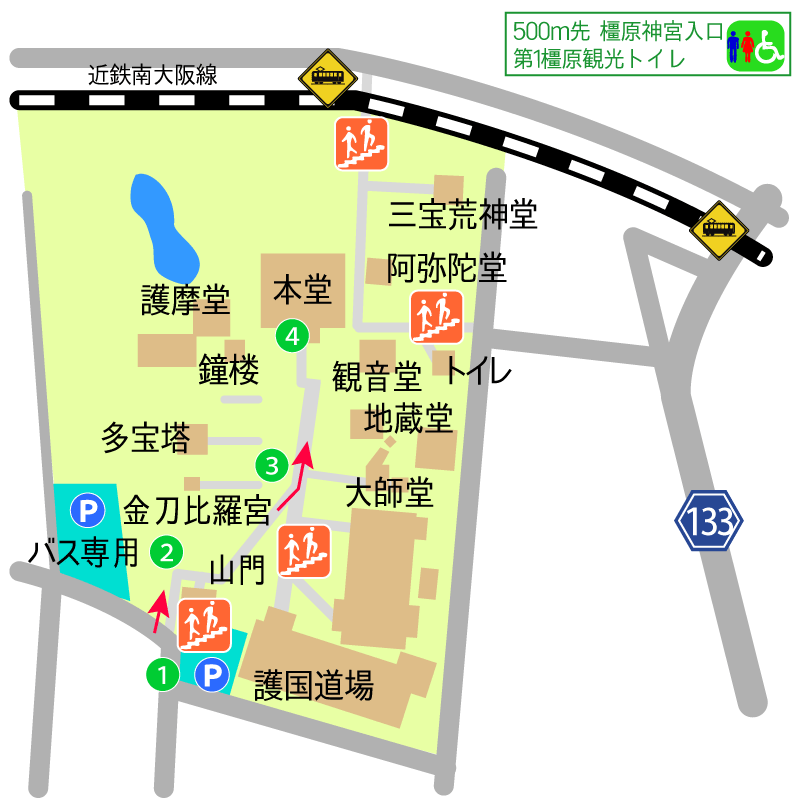
| 山門 駐車場(普通車・バス専用) 護国道場 金刀比羅宮 多宝塔 鐘楼 護摩堂 大師堂 地蔵堂 観音堂 本堂 阿弥陀堂 三宝荒神堂 トイレ 奈良県道133号戸毛久米線 近鉄南大阪線 第1橿原観光トイレ |
移動のしやすさ
★★★★☆
バリアフリーの状況
久米寺の山門には石段を迂回するスロープがついており、そのまま本堂へ続く石畳に接続している。そのほかも参道部分に石畳、他は玉砂利が敷かれ、ほぼ平坦となっている。ただし、裏手(北側)の橿原神宮方面から踏切を渡って境内に入る場合や、右手(東側)の市道からトイレ脇を通って境内に入る場合は階段があるので注意のこと。また、境内のトイレは身体障害者向けではないが、踏切を渡って500メートル先の橿原神宮駐車場入口にバリアフリーの「第1橿原観光トイレ」がある。
周辺の名所・観光スポット
橿原神宮
「橿原神宮」は、「久米寺」北側の畝傍山麓にある神社で、初代天皇である神武天皇とその后を祀ります。神武天皇即位の地として明治23年(1890)に創建されたもので、北側には神武天皇陵と治定される四条ミサンザイ古墳があります。
【身障者用トイレ・駐車場・スロープ・車椅子貸出あり】
■参考リンク:https://kashiharajingu.or.jp/

 人生で一度は行きたい 関東の神社 (ぴあMOOK)
人生で一度は行きたい 関東の神社 (ぴあMOOK) 


