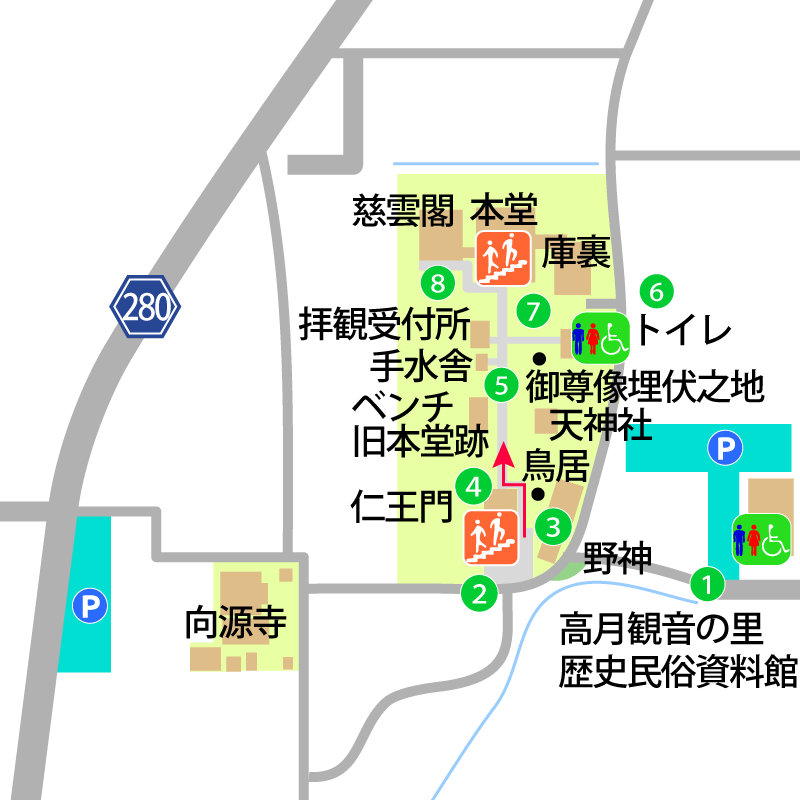渡岸寺観音堂は、滋賀県長浜市にある浄土真宗向源寺の飛地境内にある仏堂で、国宝の十一面観音が祀られています。聖武天皇の勅願により僧泰澄が十一面観音を刻み安置したのがはじまりといわれ、姉川の戦いの際には本尊が土中に埋められて難を逃れました。
旅行先について
地図
旅行先の概要
| 御本尊 | 阿弥陀如来 |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県長浜市高月町渡岸寺50番地 |
| 交通 |
北陸自動車道「木之本IC」又は「小谷城スマートIC」から車で10分 JR北陸本線「高月駅」から徒歩10分、又は「長浜駅」から湖国バス(木之本田村線)乗車30分、「国道渡岸寺」バス停下車、徒歩10分 |
| 拝観料 | 仏像拝観500円、小学生以下無料 |
| 駐車場 | 境内100メートル東側の高月観音の里歴史民俗資料館敷地内、150メートル西の県道280号線脇にそれぞれアスファルト舗装された無料駐車場あり |
| URL | https://douganji-kannon.sakura.ne.jp/ |
| 連絡先 | 渡岸寺観音堂国宝維持保存協賛会 0749-85-2632 |
歴史・由来
渡岸寺観音堂は、滋賀県長浜市にある浄土真宗向源寺の飛地境内にある仏堂で、国宝の十一面観世音菩薩像や重要文化財の大日如来像などが安置され、地域で管理されています。
もとは慈雲山光眼寺と称する天台宗の寺院で、天平8年(736)に天然痘が流行した際、聖武天皇の勅願で僧・泰澄が十一面観世音菩薩の像を刻み、一宇を建てて除災招福を祈願したのがはじまりとされます。
元亀元年(1570)に起きた浅井・朝倉連合軍と織田・徳川連合軍による「姉川の戦い」では、兵火により堂宇は灰燼に帰したものの、観音像は村民らが土中に埋めたため難を逃れたといい、境内には「御尊像埋伏之地」の石碑が建てられています。この後、光眼寺は廃寺となり、代わりに浄土真宗の向源寺が創建されました。
明治初期の廃仏毀釈を経た明治21年(1888)、宮内省に図書頭・九鬼隆一を委員長とする臨時全国宝物取調局が設置され、滋賀県内の社寺を皮切りに各地で宝物調査事業が実施されますが、この地を訪れたアーネスト・フェノロサが観音像を絶賛したことから、明治30年(1897)には旧国宝の指定を受けました。その際、地元の共有となっていた観音像は、管理者を明確にするため向源寺の所属となり、本堂や庫裏も再建されて現在に至ります。
国宝の十一面観世音菩薩立像は、ヒノキの一木造で平安時代初期の作とみられており、右足を浮かせ腰を左に捻った女性的な姿で、像の裏側に位置する悪を笑い飛ばすといわれる「暴悪大笑面」の彫刻が印象的です。なお、火災から文化財を守るため、本堂の脇には仏像を安置する鉄筋コンクリート造の収蔵庫が併設されています。
車椅子で旅行するポイント
| 高月観音の里歴史民俗資料館 野神 仁王門 鳥居 天神社 旧本堂跡 ベンチ 手水舎 トイレ 御尊像埋伏之地 拝観受付所 慈雲閣(収蔵庫) 本堂 庫裏 向源寺 滋賀県道280号井口高月線 |
移動のしやすさ
★★★★☆
バリアフリーの状況
渡岸寺観音堂は平坦地にあり、入口の仁王門に段差があるものの、裏手に迂回できる石畳の通路が整備されているので、本堂の手前までであれば移動に支障はない。ただし、仏像拝観は本堂の階段を上り、回廊を通って脇の慈雲閣(収蔵庫)に出るのが通常のルートであり、収蔵庫の外にもスロープはあるものの、使用可能かどうかは不明。境内には車椅子用トイレもあるが、現在工事中で使用できない。
周辺の名所・観光スポット
高月観音の里歴史民俗資料館
「高月観音の里歴史民俗資料館」は、昭和59年(1984)に開館した地域資料館で、「渡岸寺観音堂」の近くにあります。館内では観音像を中心とした仏教美術、高月地区の歴史と民俗、地元出身の儒学者・雨森芳洲と朝鮮通信使などをテーマとして、彫刻その他の工芸品、古文書、民俗資料の実物やパネルなどを展示しています。
【スロープ・身障者用トイレ・車椅子貸出あり。手帳提示で障害者本人と付添人1人無料。】
■参考リンク:https://www.city.nagahama.lg.jp/section/takatsukirekimin/index.html

 日本全国 一の宮 巡拝パーフェクトガイド
日本全国 一の宮 巡拝パーフェクトガイド