如意寺は、京都府京丹後市にある真言宗の寺院です。久美浜湾の最奥部に位置し、奈良時代に行基が彫ったとされる十一面観音を本尊としています。8月の本尊会は「千日会」と呼ばれ、この日にあわせ「千日会観光祭」として打ち上げ花火や大文字点灯、精霊流しなどが行われます。
旅行先について
地図
旅行先の概要
| 御本尊 | 十一面観世音菩薩 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京丹後市久美浜町1845番地 |
| 交通 |
北近畿豊岡自動車道「豊岡インターチェンジ」から車で30分 京都丹後鉄道宮豊線「久美浜駅」から徒歩15分 |
| 拝観料 | 無料 |
| 駐車場 | 山門前に砕石敷き、県道挟んで反対側の久美浜湾沿いに砂地の無料駐車場あり |
| URL | https://www.nyoiji.com/ |
| 連絡先 | 如意寺 0772-82-0163 |
歴史・由来
「如意寺」は、京都府京丹後市にある真言宗の寺院です。久美浜湾の最奥部、京都府景観資産「京丹後市久美浜湾沿岸の商家群と街並み景観」に選定された古くからの市街地の西隣に位置します。
奈良時代の天平年間に行基が開基したと伝えられ、行基が一刀三礼して彫ったとされる、高さ2尺8寸の十一面観世音菩薩立像を秘仏本尊としています。
『京都府熊野郡誌』によれば、行基がこの地を訪れた際、山上より火が出て海に入り、海より火が出て山に登りました。これは太刀宮(神谷神社)に納められている丹波道主命の宝剣が沈没する兆しであるとして、海士に頼んで網を引かせたところ、海中から如意宝珠が見つかったため、伽藍を建立して宝珠を納め、「宝珠山如意寺」と称したのがはじまりとされます。この丹波道主命は崇神天皇の時代に諸国平定のために派遣された四道将軍のひとりであり、太刀宮の主祭神です。
鎌倉時代の永仁3年(1295)には、伏見天皇が藤原定成(世尊寺定成)を勅使として勅額を下賜しました。能書で知られる藤原定成が揮毫したことは裏面の墨書から明らかであり、鎌倉時代の典型的な世尊寺流の書体を残す貴重な工芸品のひとつとして、京都府指定有形文化財の指定を受けています。
室町時代の応永34年(1427)、兵火に遭って伽藍のほとんどを焼失しますが、その後復興されており、現在の境内には、眼病平癒の御利益があるという本尊を安置する「本堂」、弘法大師爪彫りと伝える日切不動尊を祀る「不動堂」などの建物があります。なかでも昭和58年(1983)に新築された「不動堂」は、和様・唐様・天竺様を折衷した重層宝形造という日本唯一の建築様式となっています。
毎年8月9日には本尊会として「千日会」が催されますが、1日の参詣で千日分の功徳が得られるとされており、多くの参詣者があります。この日にあわせて久美浜町内挙げての「千日会観光祭」も開催され、久美浜公園での1,700発にも及ぶ花火の打上げ、兜山中腹の大文字点灯、久美浜湾の精霊流しなどでにぎわいます。
また、如意寺は「関西花の寺二十五ヵ所」の第7番にもなっており、4月にミツバツツジ、9月にハギが見頃を迎え、この時期に観光に訪れる人も少なくありません。
車椅子で旅行するポイント
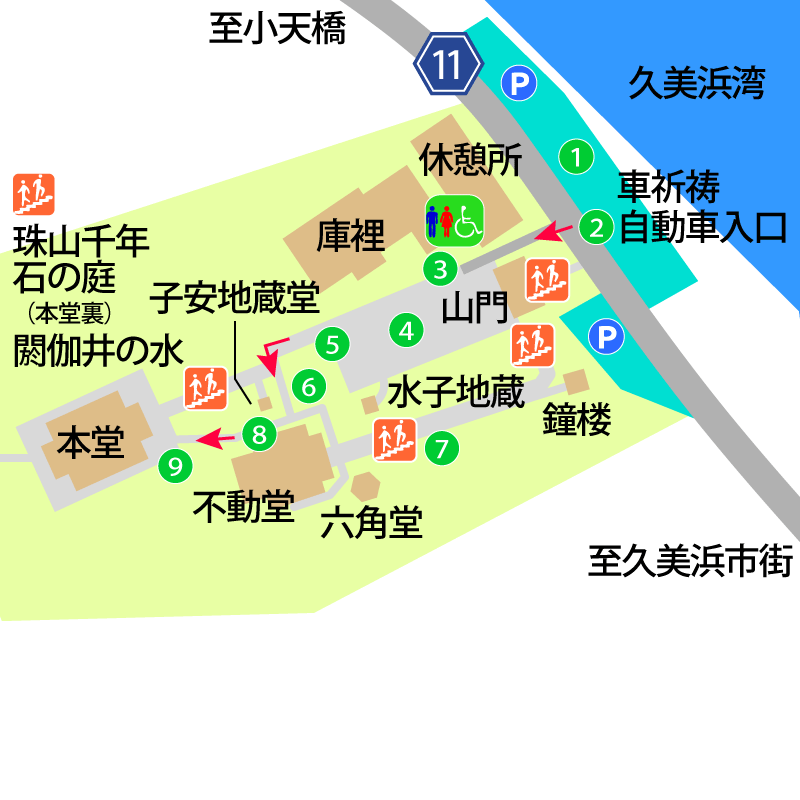
| 山門 車祈祷自動車入口 休憩所 庫裡 水子地蔵鐘楼 不動堂 六角堂 本堂 子安地蔵堂 閼伽井の水 珠山千年石の庭 久美浜湾 小天橋 久美浜市街 |
移動のしやすさ
★★★☆☆
バリアフリーの状況
如意寺は久美浜湾沿いの山麓に境内があるため、必然的に階段路を伴うが、府道から境内への自動車入口が設置されているほか、本堂や不動堂に至る参道の一部には石畳のスロープも設置されている。その他の境内の多くは平地だが玉砂利敷きのため、場所によっては沈み込みに注意。身障者用トイレは女性用と共用で休憩所脇にある。
周辺の名所・観光スポット
京丹後市久美浜湾沿岸の商家群と街並み景観
「京丹後市久美浜湾沿岸の商家群と街並み景観」は、京都府景観資産に選定された、昔ながらの風景が残るエリアを指す。久美浜の町並みは中世に築かれた松倉城、続いて近世の久美浜代官所を基準に形成されており、東西に延びる街道沿いに短冊形の区画の商家が並んでいる。地区内には廻船業で栄えた「豪商稲葉本家」、古代の磐座が残る「神谷太刀宮」のほか、昭和初期に建てられた「久美浜公会堂」や「旧久美浜役場」などのレトロな建物もある。
【久美浜公園・浜公園に身障者用トイレあり】

 人生で一度は行きたい 関東の神社 (ぴあMOOK)
人生で一度は行きたい 関東の神社 (ぴあMOOK) 







