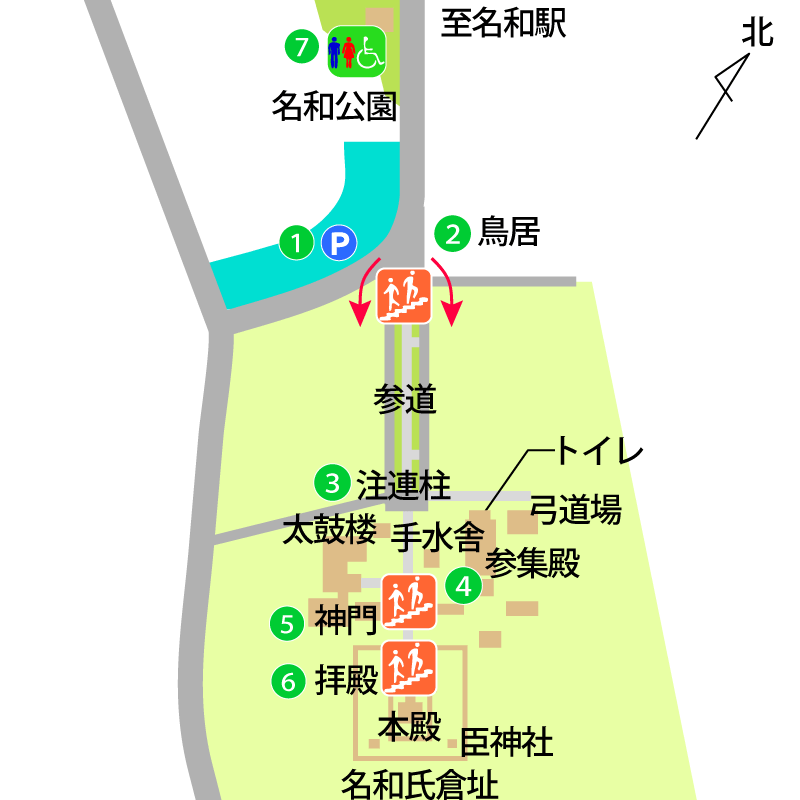名和神社は、鳥取県西伯郡大山町にある旧別格官幣社で、名和長年を主祭神とする、いわゆる「建武中興十五社」の一つです。名和長年は配流地である隠岐島から脱出した後醍醐天皇を迎え入れ、「建武の新政」に大きな功績があったことから、明治時代に神社が創建されました。
旅行先について
地図
旅行先の概要
| 御祭神 | 名和長年 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取県西伯郡大山町名和556 |
| 交通 |
山陰自動車道「名和IC」から車で5分/JR山陰本線「名和駅」から徒歩5分 |
| 拝観料 | 無料 |
| 駐車場 | 一の鳥居の道路挟んで反対側にアスファルト舗装された無料駐車場あり |
| URL | https://www.nawajinja.or.jp/ |
| 連絡先 | 名和神社 0859-54-2260 |
歴史・由来
名和神社は、鳥取県西伯郡大山町にある旧別格官幣社で、名和長年を主祭神とする、いわゆる「建武中興十五社」の一つです。
元徳3年(1331)に「元弘の変」を起こした後醍醐天皇は、鎌倉幕府打倒に失敗して隠岐島に流罪となりましたが、元弘3年(1333)に隠岐島を脱出し、名和長年によって船上山に迎え入れられました。「船上山の戦い」で隠岐守護・佐々木清高の軍勢を破ったのをはじめ、各地で幕府軍に勝利して鎌倉幕府を滅亡させた後醍醐天皇は、京都に帰還して「建武の新政」を始めました。
その後、「建武の新政」は足利尊氏の謀反によりわずか3年ほどで崩れ去り、建武3年(1336)、九州から東上した尊氏の軍勢は、「湊川の戦い」を経て洛中に侵攻しました。その際、名和長年は京都の鷺ノ森から大宮に取って返し、足利尊氏の軍勢と2百余騎で戦って討死にしたと『太平記』にはあります。
江戸時代にはすでに名和長年を祀る小祠がその屋敷跡に設けられていましたが、延宝5年(1677)、鳥取藩主・池田光仲が現在地の南東に当たる日吉坂の山王権現社地に遷座させ、社殿を建てて「氏殿権現」として祀りました。
さらに明治時代に入ると、建武中興の立役者として名和長年を顕彰するため、明治6年(1873)に旧社格で言う県社に、明治11年(1878)に「名和神社」と改称の上で別格官幣社に列格、明治16年(1883)には名和長年の米蔵跡といわれる長者原の地が寄進されて新たな社殿の造営が図られ、現在に至っています。
車椅子で旅行するポイント
| 鳥居 参道 太鼓楼 手水舎 神門 拝殿 本殿 臣神社 名和氏倉址 弓道場 参集殿 トイレ 名和公園 JR山陰本線名和駅 |
移動のしやすさ
★★☆☆☆
バリアフリーの状況
名和神社の正面参道には段差があるが、注連柱までは参道両側に車道が通じている。ただし、神門には7段の石段があるため、それ以降の拝殿や本殿には車椅子のまま移動することができない。車椅子で参拝できる範囲は境内の一部にとどまる。なお、身障者用トイレは鳥居の北150メートルの名和公園内にある。
周辺の名所・観光スポット
妻木晩田遺跡
「妻木晩田遺跡」は、鳥取県西伯郡大山町と米子市にまたがる丘陵上にある弥生時代の環壕集落跡です。およそ152ヘクタールの広大なエリアが国史跡に指定されています。現在は「むきばんだ史跡公園」として整備が図られ、ガイダンス施設「弥生の館むきばんだ」や「遺構展示館」が開設されているほか、竪穴式住居跡や四隅突出型(よすみとっしゅつがた)墳丘墓などを実際に見ることができます。
【見学路(舗装済)・身障者用駐車区画・多目的トイレ・点字ブロック・車椅子及びシルバーカー貸出あり】
■参考リンク:https://www.mukibanda.jp/

 全国御朱印大事典
全国御朱印大事典