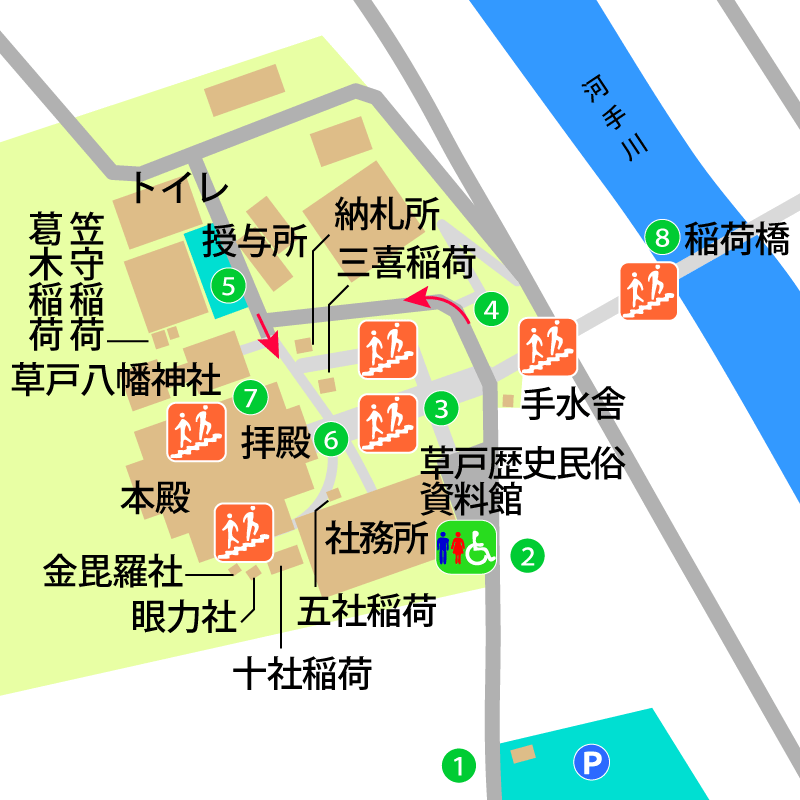「草戸稲荷神社」は、広島県福山市にある神社で、弘法大師が開基した明王院の鎮守として創建されたといわれます。中世には門前町として芦田川の中洲に「草戸千軒」が栄えました。戦後に懸崖造りの社殿に建て替えられ、福山の町並みを一望できる名所となっています。
旅行先について
地図
旅行先の概要
| 御祭神 | 宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)・保食神(うけもちのかみ)・大己貴神(おおなむちのかみ) |
|---|---|
| 所在地 | 広島県福山市草戸町1467 |
| 交通 |
山陽自動車道「福山SAスマートIC」から車で10分 JR山陽新幹線・山陽本線・福塩線「福山駅」からトモテツバス(鞆線)乗車7分、「明王院前」バス停下車、徒歩5分(運行本数僅少) |
| 拝観料 | 無料 |
| 駐車場 | 入口手前に舗装済みの第1~第3駐車場、境内に車祓用駐車場あり(無料) |
| URL | https://kusadoinari.com/ |
| 連絡先 | 草戸稲荷神社 084-951-2030 |
歴史・由来
「草戸稲荷神社」は、大同2年(807)に弘法大師空海が開基したと伝える常福寺(今の明王院)の鎮守として創建された神社です。御祭神は宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)・保食神(うけもちのかみ)・大己貴神(おおなむちのかみ)で、境内社として誉田別命(ほんだわけのみこと)を祀る草戸八幡神社があります。
もとは芦田川の中洲にあったものの、しばしば洪水の被害に遭い、寛永11年(1634)に備後福山藩の初代藩主・水野勝成により再建されました。承応4年(1655)には父である水野勝俊の病気平癒を祈願し、水野勝貞が社地を今の場所に遷したほか、4月の卯の祭礼を盛大に行ったといいます。
また、『沼隈郡誌』には、草戸に住む刀工・法華一乗が京都に上り、同じ刀工の三条宗近や稲荷の神使である狐とともに名刀「小狐丸」を鍛造し、妙顕寺に奉納したという伝承を掲げています。法華一乗はこれ以来稲荷神を崇敬し、草戸の自宅のそばに祀ったものが今の「草戸稲荷神社」であるともいわれます。
鎌倉時代から室町時代にかけて、芦田川の中州には門前町として「草戸千軒」が発達し、市が立つとともに、中国や半島との交易でにぎわいました。江戸時代以降は洪水により川の水底に沈み、福山藩士・宮原直倁(みやはらなおゆき)による地誌『備陽六郡志』に「往昔(中略)草戸千軒と云町有ける」と語られる程度でほぼ忘れ去られていましたが、戦後の発掘調査により往時の町並みが明らかとなりました。
「草戸稲荷神社」は、昭和59年(1984)に現在のような高さ23メートルの鉄筋コンクリート・懸崖造りの社殿となり、上階からは福山市街を一望することができます。初詣の参拝者数は例年30万人以上と、広島県内を代表する名所にもなっています。全国でも珍しい「大大吉」のおみくじが引ける神社としても知られます。
車椅子で旅行するポイント
| 本殿 拝殿 草戸八幡神社 三喜稲荷 笠守稲荷 葛木稲荷 五社稲荷 十社稲荷 眼力社 金毘羅社 授与所 社務所 草戸歴史民俗資料館 納札所 トイレ 手水舎 稲荷橋 河手川 |
移動のしやすさ
★★★★☆
バリアフリーの状況
草戸稲荷神社には舗装済みの駐車場や本殿手前に至るスロープ状の車道が整備されているほか、身障者用のトイレもあり、境内の移動は比較的しやすい。ただし、懸崖造りの本殿内部や稲荷橋は階段となっている。
周辺の名所・観光スポット
福山城
「福山城」は、元和8年(1622)に備後福山藩10万石の初代藩主となった水野勝成が築いた平山城です。「福山大空襲」によりほぼ焼失したものの、戦後に天守などの建物が復興されました。天守内部は「福山城博物館」となっているほか、外観も城の裏山からの砲撃に備えて一面に黒い鉄板を張った江戸時代の姿が再現されています。また、江戸時代に伏見城から移築したという「伏見櫓」が現存し、国重要文化財に指定されています。
【身障者用駐車区画・トイレ・スロープ・昇降機・エレベーターあり。障害者及び介護者は入館無料。】
■参考リンク:福山城博物館

 一生に一度は行きたい日本の神社100選 (TJMOOK)
一生に一度は行きたい日本の神社100選 (TJMOOK)