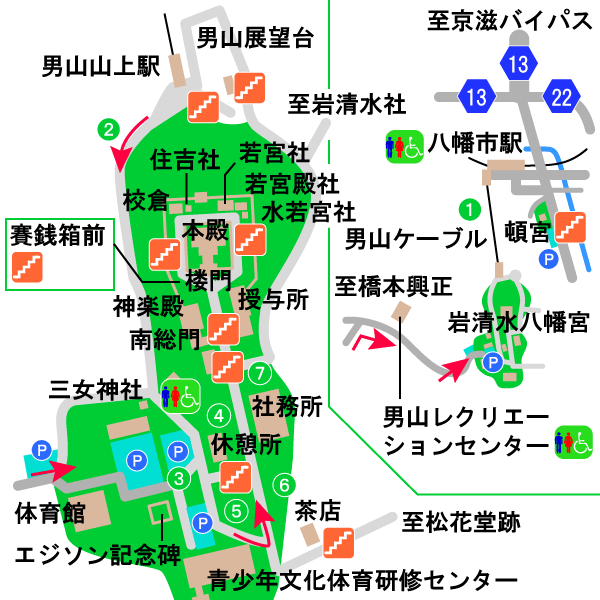石清水八幡宮は、応神天皇を祀ることから伊勢神宮とともに皇室の宗廟となっており、八幡造の本殿は国宝にも指定されています。宇佐神宮・筥崎宮・石清水八幡宮を「日本三大八幡宮」と称することもあります。吉田兼好の『徒然草』にも登場し、国語の教科書でおなじみです。
旅行先について
地図
旅行先の概要
| 御祭神 | 誉田別命 (応神天皇)、比咩大神 (宗像三女神)、息長帯姫命(神功皇后) |
|---|---|
| 所在地 | 京都府八幡市八幡高坊30 |
| 交通 |
男山ケーブル(京阪電車お客さまセンター 電話:06-6945-4560)「八幡市駅」からケーブルカーで約3分、「男山山上駅」下車、徒歩約10分 京滋バイパス「久御山淀IC」から頓宮脇の「石清水八幡宮山麓駐車場」まで車で約5分、頓宮から徒歩(登山)で約20分 または京滋バイパス「久御山淀IC」から山頂駐車場まで車で約15分 |
| 拝観料 | 無料 |
| 駐車場 | 頓宮(階段あり)脇の「石清水八幡宮山麓駐車場」(普通車500円)を利用し徒歩(登山)またはケーブルカーが一般的なルート 身障者車両は男山レクリエーションセンターを目印にして橋本興正の団地内の街路から進入し、山頂駐車場(無料)に駐車を推奨 |
| URL | 石清水八幡宮 |
| 連絡先 | 石清水八幡宮 075-981-3001 |
歴史・由来
石清水八幡宮は、京都府八幡市の男山に鎮座する神社で、応神天皇を祀ることから、伊勢神宮とともに皇室の宗廟とされており、皇城鎮守の「二十二社」のひとつでもあります。
平安時代の貞観元年(859)、南都大安寺の僧・行教が託宣を受けて宇佐神宮(大分県宇佐市)から八幡神を勧請し、翌貞観2年(860)、清和天皇が社殿を造営したのがはじまりとされています。
このため、宇佐神宮・筥崎宮・石清水八幡宮をあわせて「日本三大八幡宮」と称されますが、「石清水」という社名は、もともと男山に鎮座していた石清水山寺(現在の石清水社)によるものといわれています。
吉田兼好の『徒然草』第52段には、石清水八幡宮を参拝していないのを心残りに思った仁和寺の僧侶が、早合点して山麓にある摂社の高良神社や極楽寺だけを参拝し、男山山頂にある石清水八幡宮の本社を参拝せずに帰ってきてしまった話を載せており、かつて神仏混交で「男山四十八坊」とよばれたほど一山の建物が多かった様子がうかがえます。
また、源頼義が前九年の役にあたって石清水八幡宮を大阪や鎌倉に勧請し、のちの壺井八幡宮や鶴岡八幡宮となるなど、武家の信仰も篤く、そのほかにも各地に勧請されて八幡信仰が広まりました。
石清水八幡宮の境内は国史跡であるとともに、八幡造の本殿をはじめとする建造物は国宝にも指定されています。
車椅子で旅行するポイント
移動のしやすさ
★★☆☆☆
バリアフリーの状況
一応は身障者トイレ、スロープなどもあるにはあるが、本殿手前には階段が数か所(南総門前8段、社務所先4段)あるほか、ケーブルカーを降りてからのスロープ参道も傾斜がきつく長いため、必ず複数介助が必要。山頂駐車場も住宅街を通るわかりにくい道となっている。社務所に事前連絡すれば手伝ってはもらえるため、車椅子での参拝は不可ではないものの、国宝建築の宿命で、移動は容易とはいかない。
周辺の名所・観光スポット
今城塚古代歴史館
大阪府高槻市が設置する施設で、継体天皇の本当の陵墓ではないかとされる巨大前方後円墳の今城塚古墳、周囲の三島古墳群の出土遺物などを展示するほか、体験学習などもできるようになっています。【バリアフリー施設】
■参考リンク:今城塚古代歴史館

 一生に一度は行きたい日本の神社100選 (TJMOOK)
一生に一度は行きたい日本の神社100選 (TJMOOK)